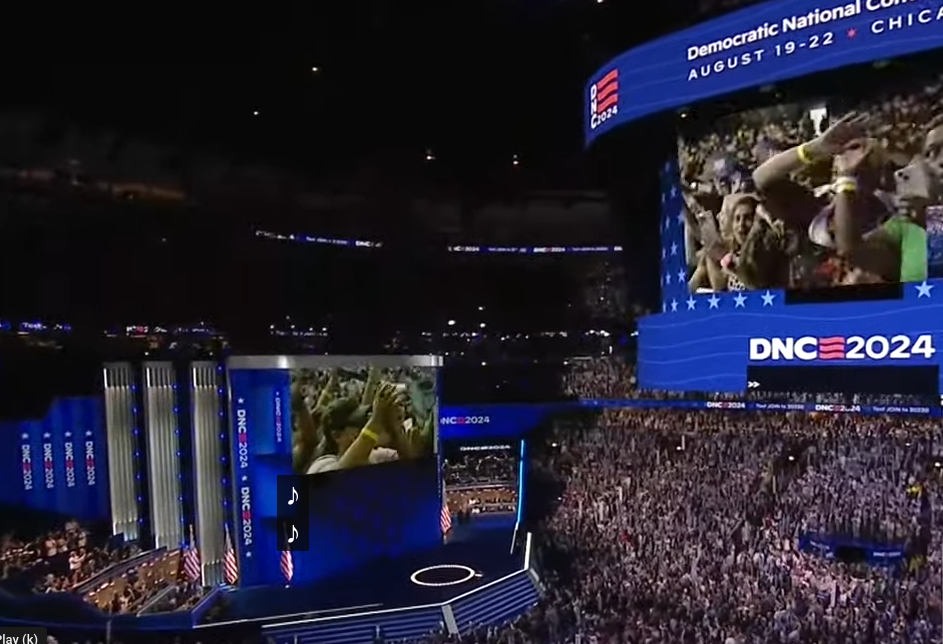
8月6日(現地時間)のフィラデルフィアでの副大統領候補ティム・ウォルツ (Tim Walz) のお披露目から、デトロイト、ラスヴェガス、途中をいくつか飛ばして8月16日のノースカロライナ、そして翌週19日から22日までの民主党全国大会 (DNC=Democraic National Convention) (highlits: Day1, Day2, Day3, Day4) 等、「主演」カマラ・ハリス、「助演」ティム・ウォルツの連続「テレビ映画」を、ライブと録画で全部観た。
「テレビ映画」ちょうどそのまえの8月4日、 ジェレミー・レナー主演のテレビ映画『メイヤー・オブ・キングスタウン』(Mayor of Kingstown) の「シーズン3」の最終「エピソード 10」を見終わったところだったので、別の「テレビ映画」を見る気分だった。
『メイヤー・オブ・キングスタウン』は、「刑務所が町の最大の産業である「キングスタウン」(この名では実在しない)を舞台に、「ありきたりの」行政や保安では犯罪や暴動を抑えることができない状況をマイク・マクラスキー(ジェレミー・レナー)が腕力と巧緻で切り抜けようとする犯罪ドラマ。しかし、「シリーズ1」はそのどぎつさにおいて新鮮味があり、「シリーズ 2」もつきあってしまったが、今シリーズでは、パターンの繰り返しのようで退屈した。
「メイヤー」(Mayor)というのは、いわば皮肉で、マクラスキーは正式の市長ではない。いわばヴァーチャルな市長である。最近ますます発言が支離滅裂になってきたトランプにとっては、アメリカ合衆国は、目下、「キングスタウン」状態にあり、自分はマクラスキーのような役割を果たしているのだと言いたげである。が、マクラスキーは、トランプのような口先三寸の男ではなく、やることは断固として実行する。トランプが願望しても、なれないキャラクターである。
折りに触れて書いているように、最近のアメリカテレビ映画は、いい線を行っている。ジョエル・エドガートン主演の『ダーク・マター』 「シーズン 2」(Dark Matter) は、5月8日から6月26日まで9回にわたって公開されたが、「暗黒物質」(dark matter)を作ってしまった科学者ジェイソン・デスセンが、みずからタイムスリップの実験を繰り返すうちに、変身日時の異なるたびに生まれた複製の自分が「現在」につぎつぎに回帰してくるというプロットで、これまでのタイムスリップものとは異なる新味を出していた。無数の「自分」が複製され、たがいに闘う事態にいたるシーンは、「ミーム」の増殖という事態を視覚化したような感じで、なかなか面白いと思った。
今年の2月27日に始まり、4月23日にエピソード10が完結した『SHOGUN 将軍』(Shogun) は、真田広之の、俳優としても製作者としても満を持した秀作だが、このシリーズは、第76回エミー賞の25部門にノミネートされた。
アンナ・サワイ

最近のカマラ・ハリスの急速な「活躍」ぶりを見ながら思い出したのは、このテレビシリーズで主演女優的な役割をはたしたアンナ・サワイだ。サワイは、一見、ダイジョブかな?と思わせながら、回を重ねるごとにますますよくなり、豊臣の兵士を相手に薙刀を振り回す「エピソード9」では、なかなかの「存在感」を見せた。とはいえ、アンナ・サワイの「存在感」は、「コンビニの味」の存在感である。
が、こういう言い方ではわからないかもしれないので、スティーヴン・コルベールのThe Late Showのゲストとしてしゃべるアンナ・サワイをみてほしい。必見。このテイストは、カマラ・ハリスの「コンビニの味」につながっている。
わたしは、「テレビ映画」というものを、劇場のイスに座り、大スクリーンで見る「映画」に対比する。いま挙げた『SHOGUN 将軍』で言えば、真田広之や戸田広松役の西岡徳馬、落葉の方の二階堂ふみは、みずから蓄積した「映画的」アウラを土台にした演技をし、「コンビニの味」とは一線を画する。石堂和成役の平岳大は、演劇系の蓄積、文太郎役の阿部進之介はテレビ系の蓄積が演技のリアリティの参照点になっており、依然として、「コンビニの味」よりふるいリアリティを表現する役者たちである。面白いのは、ロートルのなかでは唯一、樫木藪重役の浅野忠信だけが「コンビニの味」をも意識した演技をしていて、さすがと思った。
「コンビニの味」論再説ここで言う「コンビニの味」とは皮肉ではない。それは、複製可能性がますます亢進する現代の実在感であり、リアリティの最新状態である。これについては何度も書いている(→旧論1、旧論2)ので、ここでは省略するが、本欄をGoogle翻訳で読んでくれている海外の読者(本当にいるのだ)には、理解しがたい表現かもしれない。メールをくれれば、いくらでも説明します。
要するに、わけのわからない/あるいは「由緒ある」「外部」や「超越」をアウラとしてあがめて、それを頼りにしてリアリティを保持しようとするのではなく、内在的なロジックや振動のなかで生まれるリアリティである。「ミーム」(meme) という概念が、リチャード・ドーキンスをはるかに越えて――いわばmemeがみずからmemeして――使われ、複製可能性が存在全体に拡大される時代・社会の気分であり、文化である。
カマラの笑い

カマラ・ハリスの笑いはオフビートである。通常の笑い解釈ではカバーできない。一般に、笑顔をたやさないひとは苦労人である。周囲に気を使わなければならない生い立ちだったりする。プレゼンでの笑顔は、日本では好感をもたれても、英語圏ではそうではない。自信のない奴と思われたりする。放送のキャスターがニコリともしないのは異常ではないのだ。が、カマラ・ハリスの笑いは、そういう笑いの論理をはずれている。大会で何度も講演するうちに「しまり」が出てきたが、これは、深刻な問題を話すときも笑っているという非難への対応だろう。基本的に、彼女から笑いをうばうことはできない。参考→Is Kamala Harris's LAUGH a problem for the Democrats?!
チャーリーXCXの「brat」

7月22日、チャーリーXCXが、「kamala IS brat」とXしたのが、ミーム化して、その意味が議論を呼んだ。日本語訳では、「カマラこそイケてる悪ガキだ」などと記されているが、「イケてる」と言うだけでは、どんなにイケてるのかがさっぱりわからないから、日本語訳にはならない。チャーリーXCXは、当然、彼女の新アルバム『brat』にひっかけてXしたわけだが、わたしに言わせれば、チャーリーXCXの音楽は、そもそも「コンビニの味」である。だとすれば、Kamala IS bratは、《カマラこそコンビニの味だ》という和訳になる。これならば、特定のキャラだけでなく、そのライフスタイルやカルチャーをも規定できるようになる。
ローレル&ハーディの映画的記憶
副大統領候補に選ばれたティム・ウォルツも、笑うひとである。が、彼の笑いは普通の笑いであり、真顔になったとき、その対比が気になったりする。この対比は、カマラの笑いを特異性のほうにエスカレートさせるのではなく、適度に薄め、バランスを取るのに役立つ。ウォルツは、よき「番頭」である。ウォルツは、ZやXよりももっとまえの世代の「アメリカ人」を思わせる。否定的なことより肯定的なことを言い、笑顔や夢のある話をする。「連帯」や「共有」を強調し、それを自身の体で表現する。演説でも、感謝の身ぶりが多様であり、ハリスが自分を信用して副大統領に誘ってくれたことをくりかえし表現し、トランプやその一党・族にはない融和と歓びの気分を生み出す。これは、副大統領候補として最有力だった、ペンシルベニア州のジョシュ・シャピロ知事には出来ない芸当である。彼は、いつも「主役」をやりたがるタイプだ。

カマラ・ハリスとティム・ウォルツのコンビは、ハリウッド映画の記憶のなかでは、コメディーシリーズの『ローレル&ハーディ』(Laurel and Hardy)のスタン・ローレルとオリヴァー・ハーディを思い出させる。『ローレル&ハーディ』は、テレビでくりかえし上映されてきたので、子供時代にこのシリーズを観た50代、60代のアメリカ人が多数いるだろう。ヤセと太目のコンビという外的印象の記憶は、ハリスとウォルツにとって、プラスに作用するだろう。
否定の逆説
トランプが、近年ますます、自分以外の者、自分が創設したもの以外は「全部ダメ」、「悲惨」(disastrous)だと言い続けたために、「夢」をいだきたい者はトランプの信奉者になって、夢を彼に託するか、トランプを信じない者(こちらのほうが多数派)は、逆に、そこまではひどくないだろうと思うようになった。その意味ではトランプは、「アメリカン・ドリーム」を逆説的に救出したとも言える。
だから、いまの時代は、トランプを否定すると同時に「アメリカン・ドリーム」を呼び戻すにはいいチャンスではある。カマラ・ハリスの一党は、まさに、こういう点に注目している。「コンビニの味」とは、否定のはての肯定であり、いま "Dream" や”Freedom" を叫ぶことは、ありもしなかった「よきアメリカ」をふりまわして同じ言葉を地声で叫ぶMAGA主義者とはまったく方向がちがうのだ。
コンヴェンション
8月19〜22日の民主党の党大会は、ビヨンセかテイラー・スイフトがサプライズで出るという噂が流れたが、実際には、「余興」的な要素は極力おさえ、カマラ・ハリスの「スター誕生」に専念した。エンタメよりも啓蒙講座である。プロットとしては、トランプという「敵」がはっきりしているから、彼と副大統領候補 JD・ヴァンスが推進する「プロジェクト2025」反対のテーマのもと、トランプの嘘三昧のメディアクリップを次々に表示して酷評して、「興行」というよりもメディアファーストのフレームワークを作ろうとした。
「コンヴェンション」(Convention) であるからある種の「興行」的な型があり、順繰りに話し手が替わり、誰もが絶叫調の政治演説になり、あいだに芸能的な余興が入り、最後にトリ(真打ち)が登場するといった形式は、民主党も共和党も同じである。あえて比較すれば、共和党のRNC(全国党大会)のほうが、「興行」的であり、民主党のはカンフェランス的である。そして、民主党のコンヴェンションのほうが明るく、歓びと活気に満ちていた。
Freedom
ビヨンセが、『Freedom』を無断で党大会に使った共和党=トランプにクレームをつけ、その一方で、カマラ・ハリス=民主党にはその使用を許可したのは、ビヨンセのイデオロギーとも無縁ではないが、同時に、ここで歌われる「Freedom」は、共和党=トランプが主張する「Freedom」とは違うということをはっきりさせた。
カマラ・ハリスは、演説のなかで、トランプの一党が言う「Freedom」は、まずはトランプ自身、そして大富豪とトランプのオトモダチのための「自由」であって、個々人がみずから選ぶ自由ではないと明言した。

わたしは、歌のなかでFreedomという言葉を聴くと、なぜか、アレサ・フランクリンが映画『ブルース・ブラザース』で歌ったシーンを思い出す。そして、その記憶のなかでビヨンセの『Freedom』(色々なヴァージョンがあるが、そういうことも含めて)を聴くと、これは「コンビニの味」だなと感じる。アレサの歌唱は、装置や音響効果よりも彼女の身体的な要素に依存しているが、ビヨンセの『Freedom』は、彼女の歌と身体だけではなく、映像や仕掛けと連動して起動する。ある意味、彼女の「肉体」そのものはどうでもよいのである。
映画のなかのアレサ・フランクリンの歌唱は、1968年の元歌「Think」がこの映画で「再演」されたことで、彼女の「ブルース魂」つまりは「アウラ」を剥ぎ取られているが、映像や補助的なパフォーマンスや仕掛けがなくても、直接、公民権運動や新左翼運動の時代の「Freedom」につながっている響きを残している。しかし、そういう「アウラ」は、たちまち消滅するのであり、それがあたかもいつまでも永続しているかのごとく主張することが、馬鹿げているのである。
民主とはファミリー主義か?
民主党の諸イヴェントを観ていると、アメリカの、とりわけ民主党の想定する「民主主義」とは、ファミリーが単位であるという点がわかる。共和党は、トランプが家族関係を誇れないという内部事情もあって、“わたしたちはこんなにすばらしい家族をもっている„といった主張をくりかえすことができないが、民主党は、これでもかこれでもかとファミリー賛美を基本プロットにした。
まあ、ある意味、他者とつながることの出来る個人の存在は「健全」で「穏当」な発想かもしれない。しかし、いま、個人が複数多数に「ミーム」化し、個人をやっていくことが、国政以上にむずかしいといった状況が深まっているとすれば、ラディカルな民主主義の単位は、個人とその分子単位でなければならないだろう。しかし、こうなると、トランプのように、内なる「個人」だけを尊重し、その内部の葛藤や悶着を外部つまりは他人・他者のせいにするという新利己主義が跋扈しかねない。
メロドラマこれまでのところ、カマラ・ハリスとその一党は、ハリウッド式のファミリーテレビメロドラマの立ち上げに成功した。DNCの最終日のトリを演じたカマラ・ハリスのスピーチは、パワフル、コンパッション、ジョイにあふれた「感動」の30分との評価を受けたが、その前日(8月21日)には、ウォルツ自身、あるいは企画者たちが予想しなかったであろう「感動」シーンを生み出すことにも成功した。ウォルツは、すでに彼の息子(Gus)が、NLD (Nonverbal Learning Disorder、非言語学習障害)とADHD(Attention deficit Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動症)を患っていることを公開している。それに対して彼が、障害を治療によって克服するよりも障害とともにその日々を楽しむようにさせてきたこともすでに語っていた。

ティム・ウォルツの演説を聴く民主党の面々は、このことを承知していたはずだが、観客席に並んだ息子が、父親の演説を聴いてこうまで感動を示すとは予期しなかったようだ。ライブ映像を観ていたら、右側に流れる書き込みに、「ウォルツ、泣き虫一家」、「泣くな、クソ」なんて文字が見えたが、これらは、事情を知らない視聴者であろう。ネットショウのホストやXのユーザーのなかで、このシーンを酷評して、あとで「謝罪」したり、削除をしたりするケースもあったらしい。
「左翼」から「極左」まで


それは、それなりに、泣かせの演出批判で対抗すればいいのであるが、今回は、アメリカにも久しぶりに祭りの気分が横溢したのは、肯定的に受け取るべきである。いっときの高揚であれ、DNCの開催まえから街頭で盛り上がっていたイスラエル・ガザ情勢への批判集会やデモも一応は「許容」され、マイナーな複数多数の運動、アメリカでは「左翼」とみなされる諸組合、そしてメディアが「極左」に分類するアレキサンドリア・オカジオ=コルテス (彼女は二大政党制の批判者である)までが、ハリスの一党とゆるい「共有項」を容認したことは、評価されるべきである。