日本語では「同じ人間」という言葉がどれほど罪責逃れのふやけた決まり文句として利用されているかをよく考えてみるべきだ。 (p.199)
国民はひとりの生きた人間〔天皇〕から、人間という内容をすっかり抜きとって、自分たちの姿を自分たちの目からいつまでも隠そうとしているのである。 (p.215)



 竹岡健一
竹岡健一
@第二次世界大戦下のドイツにおける「前線書籍販売」について―研究の意義と観点― かいろす55(1917)◆

 井上隆史
井上隆史
@対談 佐々木孝次×井上隆史 図書新聞 2017年‘‘月25日号

 ジャック・デリダ
ジャック・デリダ
@言葉にのって 林好雄・森本和夫・本間邦雄訳 筑摩書房

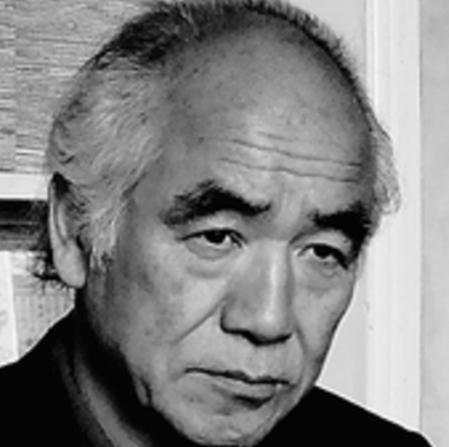 浅利誠
浅利誠
@ジャック・デリダの思い出(三) 三田文学 2017 秋季号

 矢部宏治
矢部宏治
@〈特別対談〉これが「日本の現実」だ 田原総一郎×矢部宏治 本 NOVEMBER 2017 講談社



 ジャン‐フランソワ・リオタール
ジャン‐フランソワ・リオタール
@経験の殺戮 絵画によるジャック・モノリ論 横張誠訳 朝日出版社


 エルンスト・H・ゴンブリッチ
エルンスト・H・ゴンブリッチ
@棒馬考 イメージの読解 二見史郎・谷川渥・横山勝彦訳 勁草書房

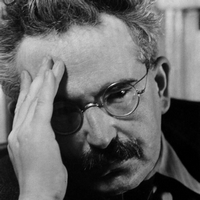 ワルター・ベンヤミン
ワルター・ベンヤミン
@ベンヤミン著作集6 円子修平訳「翻訳者の使命」 晶文社

 アントナン・アルトー
アントナン・アルトー
@演劇とその形而上学 安堂信也訳 白水社

 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー
ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー
@冷戦から内戦へ 野村修訳 晶文社

 ウィリアム・D・ハートゥング
ウィリアム・D・ハートゥング
@ブッシュの戦争株式会社 杉浦茂樹・池村千秋・小林由香利訳 阪急コミュニケーションズ

 ピーター・W・シンガー
ピーター・W・シンガー
@戦争請負会社 山崎淳訳 NHK出版


 マイケル・T・クレア
マイケル・T・クレア
@血と油 アメリカの石油獲得戦争 NHK出版


 アンジェラ・デイヴィス
アンジェラ・デイヴィス
@監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体 上杉忍訳 岩波書店

 ビル・エモット
ビル・エモット
@20世紀の教訓から21世紀が見えてくる 鈴木主税訳 草思社

 ノルベルト・エリアス
ノルベルト・エリアス
@文明化の過程(上) 赤井慧爾・中村元保・吉田正勝訳 法政大学出版局

 デイビッド・ディクソン
デイビッド・ディクソン
@オルターナティブ・テクノロジー 技術変革の政治学 田窪雅文訳 時事通信社

 チャールズ・ブコウスキー
チャールズ・ブコウスキー
@死をポケットに入れて 中川五郎訳 河出書房新社

 ダンカン・ウェブスター
ダンカン・ウェブスター
@アメリカを見ろ!〔Looka Yonder! 1988〕 安岡真訳 白水社
 「シェパードの作品の中で、われわれの前に立ちはだかるのは空っぽの地所、空虚な土地である。アメリカ的光景の果たされなかった約束、異性愛の物語〔ナラティヴ〕の崩壊した真理。土地を耕すという人民主義〔ポピュリズム〕の真理と、核家族を中心にしたマチズモとフェミニズムの構築が追い求められ、そして同時に否定される。」 (p.178) 後年俳優の「ふりをした」劇作家サム・シェパードには、そんなアメリカへの「諦め」の影がちらついていた。
「シェパードの作品の中で、われわれの前に立ちはだかるのは空っぽの地所、空虚な土地である。アメリカ的光景の果たされなかった約束、異性愛の物語〔ナラティヴ〕の崩壊した真理。土地を耕すという人民主義〔ポピュリズム〕の真理と、核家族を中心にしたマチズモとフェミニズムの構築が追い求められ、そして同時に否定される。」 (p.178) 後年俳優の「ふりをした」劇作家サム・シェパードには、そんなアメリカへの「諦め」の影がちらついていた。

 ジャック・アタリ
ジャック・アタリ
@告発される医療〔フューチャー・ライフ ミッシェル・サロモン編 辻由美訳 みすず書房所収〕

 ビル・エモット
ビル・エモット
@20世紀の教訓から21世紀が見えてくる 鈴木主税訳 草思社



 クラウス・ヘルト
クラウス・ヘルト
@地中海哲学紀行〔上〕 ミレトスからペラへ 井上克人・國方栄二・監訳 晃洋書房


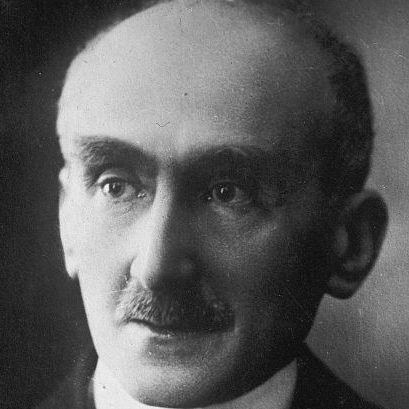 アンリ・ベルクソン
アンリ・ベルクソン
@「変化の知覚」(『思想と動くもの』所収) 河野与一訳 岩波書店

 ジョン・オニール
ジョン・オニール「子供が意識的に知っており、大人が無意識的に知っていること、それはわれわれが身体以外の何ものでもないということである。」(p.70)

 ダニエル・デフォー
ダニエル・デフォー「ブラジル人が、たいがいの病気をタバコだけで直していることを、ふと思い出した。・・・まずタバコの葉を取り、口のなかでかんでみた。初めのうちは、もう少しで気絶するところであった。そのタバコがまだ青く、強かったからである。・・・つぎに、タバコの葉をラム酒のなかに一、二時間つけておいて、寝る前に飲むことにした。最後に、私はそれを、炭火にかけた鍋の上であぶってみた。熱いのと、息がつまりそうなのとで我慢のできなくなるまで、私はその煙のそばに鼻を近づけてみた。」(p.109-110)

 マリタ・スターケン
マリタ・スターケン「免疫システムを紛争のメタファーで表現することを拒絶し」(p.415)、「免疫システムを記憶や学習、そしてもっと広げて言えば治癒の場所と思いなすこと」(p.416)。

 村上知彦
村上知彦「村上三郎の息子の知彦です。ぼくが子供の頃・・・三歳位やったらしいですけど、父は六畳二間のひとつをアトリエとして占拠してまして、作品を作り始めるとそこにこもって出てこない。ぼくは遊んでもらいたくて、仕切りになっているフスマを叩いているうちに破ってころげ出してしまった。それを見て「紙破り」を思いついた・・・と父は語っていたそうです。」(p.152)

 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー
ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー「・・読者にふりあてらる役割は、行動するものの役割ではなくて、傍観するもののそれである。雑誌がやってみせる覗き見と暴露が、読者を覗き屋〔ヴォワユール〕にしてしまう。」(p.113)

 クリス・ヘッジズ
クリス・ヘッジズ「PTSD〔心的外傷後ストレス障害〕が進むと、嗅覚が弱まる。新しい言葉を学ぶのに苦労する。ありもしない物音が聞こえる。頭の中で声が聞こえるという幻聴が起きる。」(p.195)

 ケヴィン・ケリー
ケヴィン・ケリー「「計算機」〔コンピュータ〕と呼ぶのは適当ではない。本当は「接続機」〔コネクター〕と呼ぶべきなのだ。」(p.290)

 ラッセル・ショート
ラッセル・ショート「カントは引きこもりの小鼠(ネズミ)のような男で、プロイセンの故郷の街から百マイル以上離れたことはない。」(p.135) 小ネズミじゃなくて、大ネズミかも?

 テッド・チャン
テッド・チャン「たぶんその背後にはヴィデオカメラがあるのだろう。録画にかかっているかもしれないから、それに笑顔をむけて、ちょっと手をふってみせる。現金自動支払機の隠しカメラに対しても、わたしはいつもそうしている。」(p.65)

 グレゴリー・ストック
グレゴリー・ストック「唾液ないし血液を一滴塗付けるだけでDNA塩基配列を読み取れるほど十分に信頼性のある検査法ができるのは、ほとんどまちがいないだろう。」(p.68) とは2002年の予言。いまでは、切手を舐めて貼るのも要注意。

 ラッセル・ベイカー
ラッセル・ベイカー「彼が権力を握ったのは、もしかすると名前の綴りがわりあい簡単だったからかもしれない。」(p.124) とNYタイムズの辛辣なコラムニストが言ったのはソ連のアンドロポフのことだった。生きていたらトランプについて何と言うだろう?

 高橋悠治
高橋悠治
「ピアノという最もヨーロッパ的な楽器を弾くこと、それを鍵盤上の手の舞いとして、創りなおすことができるだろうか。」
「ユダヤ教会、ビザンティン教会でも楽譜は声の抑揚をしめす手のうごきからつくられたという。」(p.227)

 ヘンリー・ミラー
ヘンリー・ミラー「私を生んだ母は、数多くの街角を通りながら、だれに声をかけられても一言も答えなかった。しかし、彼女は最後に自分をさらけ出した―私がその答えだったわけである。」(p.134)

 フレデリック・パジェス
フレデリック・パジェス「イェニー・マルクスによれば、彼女の夫は意図的に「膨大な歴史的資料をつけ加えることにした。・・・ドイツ人は分厚い本しか信じないから」」(p.232)。

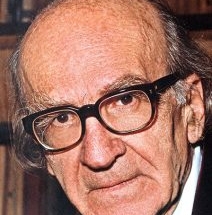 ミルチャ・エリアーデ
ミルチャ・エリアーデ「わたしの知った哲学者――じかに知ったという意味だが――の中で一番深遠なのは、かかりつけの歯科医、ドクター・ザンフィレスクですね。神経を抜いた後でこう言いました。『たいしたことはありませんよ。これからは死んだ骨を一本身に着けているだけです』。」(p.79)

 平川祐弘
平川祐弘「合衆国は憲法修正第一条の文言にもかかわらず、実質においては政教未分離の国ではないのか。」(p.78) 23年まえには批判として読んだが、わしの誤読だったらしい。

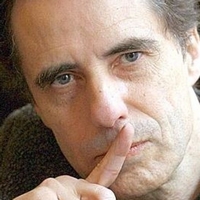 ピエール・バイヤール
ピエール・バイヤール「われわれは、多かれ少なかれ、本の一部分しか読まないし、その部分にしても、遅かれ早かれ、時間がたてば消え去る運命にある。」(p.67)

 馬場胡蝶
馬場胡蝶「その時分〔明治25年ごろ〕には、住宅難どころではなく、家主難ぐらゐなものであったのである。借家住宅ならば、山手などにはどこにでもあったといってよかった。」(p.116)

 ジェレミー・マクランシー
ジェレミー・マクランシー「今日、エスニック料理あるいは地方料理を味わう西洋人は」「「他者」を食べることによって、かれらは「自己」を再定義する」(p.370)。

 メアリアン・ウルフ
メアリアン・ウルフ「ディスレクシア〔読字障害〕は、脳がそもそも、文字を読むように配線されてはいなかったことを示す最もよい、最もわかりやすい証拠である。」(p.315) だから、手が要るのさ。

 ジャン・デ・カール
ジャン・デ・カール〔ルートヴィヒにとって〕「日記はあらゆる種類の葛藤の場であり、次々と誓いをたててはそれを破ることを繰り返す場でもあった。」(p.199)

 松本清張
松本清張「九鬼公使夫人波津子の動静を伝える当時〔1885年〕の米紙の記事がある。これは『「いき」の構造』で知られる九鬼周造が母波津子の想い出のために丹念に集めて保存しておいたもので、神戸の甲南大学文学部の所蔵である。」(p.45) このことは、清張の貴重な発見。岡倉と母との関係を婉曲的に描いた九鬼の「岡倉覚三氏の思出」にも出てこない。

 リチャード・フロリダ
リチャード・フロリダ「近代以降初めて――おそらくアメリカの歴史上でも初めて――世界の一流の科学者や知識人が、アメリカに行かない、という選択をしている」 (p.150) と書かれたのは2005年。「ブッシュすらよく見える」トランプの時代ならなおさら。

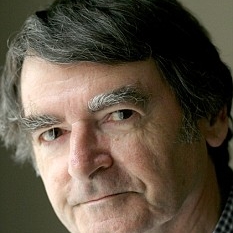 デイヴィッド・ロッジ
デイヴィッド・ロッジ「盲目は悲劇的だが、失聴は喜劇的だ。オイディプスを例にとろう。彼が自分の目をえぐる代わりに鼓膜を破ったとしてみよう。」「おそらく同情心は掻き立てるだろうが、恐怖心は掻き立てないだろう。」(p.19) アイロニカルな小説の原題はDeath Sentence(死刑宣告)をもじったDeaf Sentence(失聴宣告)。

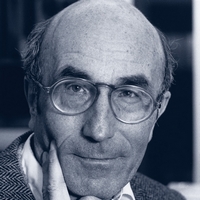 ニクラス・ルーマン
ニクラス・ルーマン「マスメディアは真実/非真実というコードには従わず、その認知的なプログラムの領域においてでさえ、インフォメーション/非インフォメーションのコードに従っている。」(p.60) なぜなら、「高見の見物人」の創造こそがマスメディアの機能だから。

 スーザン・バック-モース
スーザン・バック-モース「ベンヤミンは、「われわれは、親たちの世界から目覚めなければならない」と主張した。しかしながら、親が一度も夢を見たことがないとするなら、新しい世代に何が要求できるだろうか?」(p.261)。

 ヘルマン・ブロッホ
ヘルマン・ブロッホ「青春時代のかずかずのおもかげに覆われて最初からあたえられていなかったものは、何ひとつとして人間の手にとらえられることはできない。」(p.29)

 アシル・リュシェール
アシル・リュシェール「中世における本当の宗教は何であったか、そこのところをはっきり知る必要がある。それは聖遺物〔諸聖人の遺物やキリストあるいは聖母マリアが手を触れたとされるもの等々〕への信仰であった。」(p.47)

 カトリーヌ・マラブー
カトリーヌ・マラブー「脳はみずからに従わないということを考慮しなければならない。」(p.136)

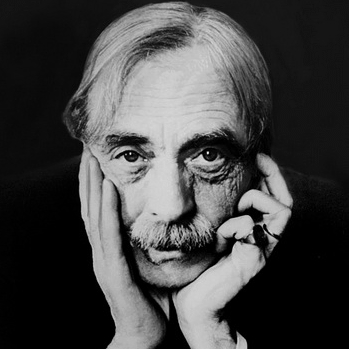 ポール・ヴァレリー
ポール・ヴァレリー「一般的にいって私の右手は私の左手を知らないのであって、その一方をもう一方で掴むとは、非-私である物体を掴むことなのだ。」(p.197)

 ノルベルト・ボルツ
ノルベルト・ボルツ「飛行機が可能になったのは、鳥の模倣を止めたときだった・・・ロボットが可能になるのは、人間の模倣を止めるときだ」(p.243)。

 ウンベルト・エーコ
ウンベルト・エーコ「ライプニッツにとって書棚の整理とは、知識を整理するのと同じことだった。」(p.415)

 ジョージ・スタイナー
ジョージ・スタイナー南米のジャングルで生き延びた老「ヒトラー」はうそぶく――「私の人種主義は、君たちの人種主義のパロディだ、飢えた物真似だよ。シオンの永遠に比べればわれわれの千年王国が何だ? おそらく私は、あらかじめ送られた偽のメシアだったのだ。私を裁くなら、君たちは君たち自身を裁かなければならない」(p.218)。

 ジョン・ランディス
ジョン・ランディスロシア問題以前にチェックメイトだな。トランプは、70~80年代のニューヨークで暮らしながら、地上げに忙しく、大ヒットの『ブルース・ブラザース』すら見てなかったんだろう。が、James Fields は見ていて、逆に利用した。

 武林無想庵
武林無想庵盲目になった無想庵のテキストは、婦人の朝子さんが口述筆記した。晩年には寝たきりで、口述した(本書に写真がある)が、ある意味、無想庵は、一生寝転んで語りのパフォーマンスをしていたのだ。だから、寝て読むと、そのその超イマ性がわかる。

 リチャード・セネット
リチャード・セネット「権力を変化せしめうる方法は、ローマの場合と同様、圧制者たちが自分のしていることの滑稽さに、気づくこと以外にない」(p.247)。邦題は本書の現在的有効性と屈折(作者のカミングアウト)を見過ごさせる。

 三島由紀夫
三島由紀夫「駒沢の考える家族とは、愛などを要せずに、そこに既に在るものだった」(p.258)――という異議は、「家族」を越えるしかないが、三島は「家族」を越えることはできなかった。

 グレアム・グリーン
グレアム・グリーン「〝しかし〟の連続から解放されて、のびのびと暮らす日が、いつ訪れてくるものか」(p.209) と主人公カースルは自問する。俺は、「しかし」より、「でも・・」かな。

 鈴木志郎康
鈴木志郎康鈴木さんの新詩集の発音を聴きたいという(日本語の読めない)ドイツの友人のために、「改稿 俺っち日本人だっちゃ」(p.206-215) をスキャンして、Google Translationで読ませてみた。誤読はあるが、「~っちゃ」言葉をちゃんと読むじゃないか。
