“みんな”映画から“オレオレ”映画へ

◆映画は劇場で見るものだと思っていたが、最近は大分心変わりがしている。というより、映画はもうネット映画しか見ないという状態だ。これは、コロナ禍で劇場に行かないあいだについた習慣というよりも、ネット映画(といっても、ここでは主としてアメリカ発の作品であるが)が活気づいていて、見ないではいられないという思いがするからである。

◆ネット映画と言っても、技術的な区別がいろいろあり、むかしのケーブルテレビジョンの流れを組むものから、IPTVのようなフォーマットによるもの等々めんどうだが、わたしが言いたいのは、劇場におもむいて観る映画と個人的にどこででも見れる(あえて言えば「トランスローカル」な)映画との違いである。ただし、ここで問題にしたいのは、そういう区別をもう一歩越えて、そのトランスローカルな映画のなかで変動が起こっているということである。
◆その変動をわたしは、「みんな」映画から「オレオレ」映画への移行という言い方で考える。この2つのタームについては、他所で論じたが、ここで言う「オレオレ」は、唯我独尊的な「俺」とは関係がない。

◆最近、大泉黒石の『俺の自叙伝』が岩波文庫に復刊されたが、その冒頭いきなり、「アレキサンドル・ワホウィッチは、俺の親父だ。親父は露西亜人だが、俺は国際的の居候だ。あっちへ行ったりこっちへ来たりしている。泥棒や人殺しこそしないが、大抵のことはやってきたんだから、大抵のことは知っているつもりだ。」と公言するように、立脚できる「自分」がある。
◆もっとも、大泉は、そういうものの存在に自信がないからこういう大言壮語的なもの言いをするのかもしれないが、オレオレ詐欺の「オレ」は、大泉のように居直る自分など全く存在しないことを自覚しているところが、大分違うのだ。だから、最初の「オレ」は、相手が知っているいるはずの「オレ」に同調させる(つまり騙す)ために、二度「オレ」をくりかえさなければならない。相手が同調してくれなければ、この「オレ」は雲散霧消する。
◆「オレオレ」は、「みんな」という共同意識以後の自己意識であり、誰も、自分の存在が確たるものだなどとは信じられない、まして他人をや・・といった状況とむすびついている。
◆劇場映画は、暗闇のなかに潜む個々の観客が、それぞれに思い、感じる差異性を保証しはするが、観客「みんな」が大枠では共感してくれることを期待している。観客が少なくても上映するのは美談だったが、それは所詮は痩せ我慢であり、最初から数人からたった一人の観客を想定した劇場映画は、すくなくとも興行主の側からは、存在しない。
◆コロナ禍で、とりわけ日本では、個人生活の国家総動員的統制が行われたが、トランスローカルなメディアがすでに浸透している環境では、映画の嗜好まで統制することは出来なかった。ちなみに、コロナ禍は、テクノロジーのもっと根源的な地盤変動の動きの一端にすぎず、その変動がコロナ禍で幾分加速したというにすぎない。リモートテクノロジーとトランスローカルなコミュニケーションは、すでに始まっていて、いまやそれが抑えようのないレベルに達している。
◆この動きのなかでは、あらゆるものがいまのトレンドで再編成されざるをえないだろう。劇場映画は、ネット映画に移行するだけではなく、いずれは、ネット映画のスタイルで再構成された劇場映画が登場するだろう。しかし、デパートが斜陽化し、ネット通販がさかえ、レストランが減ってデリバリーやセルフクッキングがさかんになるといった現象は、都市そのものの衰退を招くから、劇場自体の存続は、ますますむずかしくなる。
◆ネット映画が注目なのは、登場するキャラクターの根底だけはしっかりしているという劇場映画の前提がくずれ、スキゾ的な「人格」(人格という概念自体が成り立たないので括弧付で書く)がつぎつぎに登場するようになったからである。これは、トランプのようなキャラが政治を賑わせる動きとも無関係ではないが、以前ならドタバタコメディやサイコスリラーのようなジャンルにしか登場しなかったキャラが、メディアのなかであたりまえになってきた。
◆こういう状況では、しっかり作られた劇場映画は、精細を欠く。ネット映画に惹かれながらも、気になって見たいくつかの劇場映画のうち、面白いと思ったのは、みな瑣末な部分ばかりだった。『不思議の国の数学者』はしっかりと作られた映画だが、この映画の最終部は、パチーノが出た『セント・オブ・ウーマン』のパクリじゃないのかなんてことを思い、せっかくの「鑑賞」ができなかった。
◆『午前4時にパリの夜は明ける』(Les passagers de la nuit) は、1980年代のパリのラジオ局の話だというので期待したが、当時ホットだった自由ラジオ(ラジオ・リーブル)を完璧なまでに無視しているので、こりゃだめだと思った。ミッテラン政権誕生の時代のパリはよく知っていたが、こんな感じじゃなかった。というより、そういう写実主義的な比較が出来てしまうところがだめなのだ。

◆フランス映画では、『パリタクシー』(Une Belle Course)のほうが面白かった。先が読める作りではあるが、ドキュンメンタリーぽいところに救いがある。が、これは、「劇映画」としては「逃げ」であって、それ自体が本質的に「ドキュメンタリー」でもある「ネット映画」への逸脱だ。それは別として、92歳の乗客を同年輩のリーヌ・ルノー(Line Renaud)が演じているのには驚いた。

◆テレビを主に相当数の映画に出演していたようだが、わたしには、リーヌ・ルノーというと、まずはシャンソン歌手であり、そのむかし、東芝AngelのLPディスク(赤盤)で聴いた「パリの空の下」(Sous le ciel de paris) などの印象が刻み込まれていたので、その老年の姿に、この映画でお目にかかるとは思いもよらなかった。

◆クロネンバーグの『クライム・オブ・フューチャー』(Crimes of the Future) は、あいかわらずおどろおどろしい身体性にこだわっている監督に敬意を評したいが、もうこういう身体観ではどうにもならないということを感じざるをえなかった。しかし、この点については、もっとちゃんと論じなければなるまい。稿を改めたい。

◆昨年公開の『自由への道』(Emancipation/2022)は、「劇場映画」らしい作りのネット映画(Apple TV+) だが、奴隷時代の「実話」に基づくとするこの映画は、しなやかにつくったドキュメンタリー風の劇場映画よりも、劇場映画の古さを異化してくれる。その襟を正して見させるような作り、つまりは、こっちが「みんな」に合わせなければならない強制力を行使する作りは、ふとその見ている意識に括弧をはめると、失礼ながら「深刻」なシーンで笑いがこみ上げてしまったりする。劇場映画は、正装して聴きに行く(?)クラシックコンサートのようなものになっていることを教える。
◆劇場映画が衰退のメディアであるのは、「みんな」を相手にしようとするからである。まあ、「みんな」を相手にしているように見えてその実、「みんな」性を解体するようなことが可能なのが劇場映画でもあるが、その点で(日本の)地上波テレビよりはましかもしれない。地上波テレビは、視聴環境は個別「オレ」化したとしても、見せ方が完璧に「みんな主義」だからである。ちなみに、トランプのプロパガンダマシーンとして機能したFOXNewsは、基本においてはケーブルテレビである。だからこそ、左右を見回しながら平均値を放映する日本の地上波テレビの標準では「デタラメ極まりない」放送ができるのだ。

◆前ぶりばかりで、この文章自体が「オレオレ」詐欺的になりそうだが、これぞ「オレオレ」映画だなと思ったのは、3月に見た『ナイト・エージェント』(The Night Agent) である。これは、ネットネットしているNetflixの製作配給だが、Sony Pictures Televisionが制作しているためか、Netflixっぽい感じがない。
◆『ナイト・エージェント』の形式は、徹底した「オレオレ」主義である。もともと映画は「オレオレ」つまり意識と身体との騙しあいであり、その騙しの波長を観客のひとりひとりに同調させようとするのだが、それを「観客」というひとくくりの多数者をまとめてやろうというセコいところがもう古いのだ。その点『ナイト・エージェント』の「オレオレ」主義は、プロット自体も「オレ」と「オレ」に限定し、決してそのペア的関係を散漫に「みんな」化しない。
◆シリーズ1、エピソード1(以下S01E01のように記述する)のオープニングは、主役のガブリエル・バッソが、地下鉄の爆破テロに出遭い、犯人を追うアクションだが、バッソが演じるピーターは、マット・デイモンが演じたジェイソン・ボーンに風貌が似ていても、彼のような「不死身」の人間ではない。だから、当然のように、犯人には逃げられる。が、このシーンからして、一対一であり、「みんな」ではなく「オレオレ」関係なのだ。
◆このテロが失敗したのは、「みんな」を巻き込むテロだったからで、その後に展開する殺し屋による個別テロは、みな成功し、それをはばもうとするガブリエルとの「オレ」対決になっていく。そのいまの時代、テロも「オレオレ」であり、「一人一殺」が復活した。

◆エピソード2から出ずっぱりの殺し屋は、カップルなのだが、それぞれのスタイルを持っていて、最初はうまく行くのだが、最後には自滅に陥るのも、単にサスペンス映画のパターンだからというより、カップル性という「みんな」性(最小単位としても)がもう無理だからだった、という言い方は牽強付会だろうか?
◆ある意味、デイル(フェニックス・ライ)の方は不能で、彼がエレン(Eve Harlow)を性器的に満足させるのはペッティングしかないという制約によって、二人は単なるカップルとは異なり、「オレオレ」関係を維持しているとも言える。しかし、次第に、女が「家庭」を持つことへの願望に揺れ、いっとき、使われていない豪邸をスクウォットして住み込み、「普通の夫婦」の真似事のようなことをするにつれて、二人のそれまでの独異性が失われて行く。

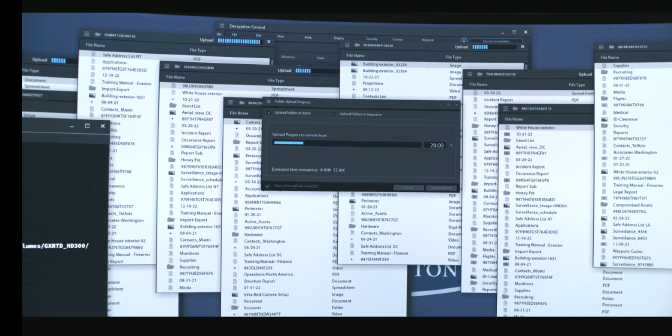
◆ピータの仕事は、FBIの緊急電話の深夜番である。エイジェントに緊急事態が起こってかかるのを受けることもある。ローズ(ルシアン・ブキャナン)は、叔父夫婦の家にいて襲われ、からくも逃れ、叔父の残した番号に電話をする。彼女は、叔父がエイジェントであったことも知らない。ここから二人の関係が始まるのだが、一見ラブストーリーの展開を思わせながら、必ずしもそうはならず、むしろ、「オレオレ」時代の愛とはどんな風になるのかいう思考を刺激しながら、話は、コンピュータに強い彼女との、べったり「みんな」主義には陥らない、内的距離を保ったコラボレイションとして進む。
◆最初からあやしげなFBIの副長官ジャミー・ホーキンス(ロバート・パトリック)だけでなく、次第にシークレットサービス、大統領主任補佐官(ホン・チャウ)、さらには副大統領、いや大統領すら、登場するどいつもこいつもが、最終的に「不信」のスキゾ的人物(というより「仮想人格」)と思われてくる展開。こうなると、ピータとローズとの関係も? 来年、シリーズ2の製作が決まったから、この「不確定性」は延々と続くのだろう。そういえば、スタイルは大分ちがうが、UKの『ザ・ディプロマット』(The Diplomat)も、スキゾ的な「オレオレ」映画であり、しかも、現在の政治状況の雰囲気を意識して取り入れているので、なかなかおもしろい。